そうしてPPL(自家用操縦士ライセンス)を取る気になったのだが、訓練校と呼ばれる教習所をどこにするかを探さなければならない。日系大手のパイロットさんたちにも聞いてみたが、皆さんガチ勢なので自社養成と言われる入社してからアメリカなどで訓練をうけた方か、航空大学校だとか崇城大学、東海大学といった具合に学校でCPL(事業用操縦士)まで取った方がほとんど、日系大手のグループ会社の若手だとアメリカだとかカナダだとかで取った方がたまにいらっしゃるという具合。
結局、インターネット検索で訓練校を探した。自分がキーワード検索をしてみつけた訓練校以外にも良いところがないかとChatGPTに調べてもらったりもした。
どの国のライセンスを取るか
パイロットのライセンスというものは、操縦する機体の登録国のものでなければならない。例えば日本で登録されている機体であればJAからはじまる登録番号が書かれていて、これを操縦するにはJCAB(Japan Civil Aviation Bureau、国土交通省航空局)のライセンスを持っている必要があり、Nからはじまるアメリカで登録されている機体はFAA(Federal Aviation Administration、連邦航空局)のライセンスが必要となる。つまり、海外で訓練を受けてライセンスを手に入れた後は自分が飛行機を借りに行きそうな場所のライセンスへの書き換えというものが必要になる。飛行機を買って維持するのにはお金がかかるので、僕はどこかのフライトクラブに所属させてもらって、そこで機体を借りることを考えている。日本国内のフライトクラブに入ることが最も多いだろうから、日本のライセンス、つまりJCABのライセンスを最終的には手に入れなければならない。
JCABのライセンスというのは、外国のライセンスから要求事項を満たしていれば書き換えが可能らしい。条件を満たしていればというのは、ICAO締結国のライセンスであることといったところから、JCABの受験資格を充足する場合というところまで様々なものがある。具体的によく問題になるのは経験した訓練飛行の内容と時間数、それからそれを証するログブックの記載だそうだ。書き換えのときに問題にならないようにするに訓練を受けるときにつけるログブックとは別にJCABに書き換えるためのログブックを用意してそれぞれ書いておくだとか、日本のルールに対して理解のある教官(CFI)にお願いするだとか色々な対策があるらしい。
訓練校選び
話を訓練校選びに戻すと、個人的には以下の4択にまで絞った。
- 日本国内の近くの訓練校
メリット:
車で30分ほどで通えるのは魅力。
座学がオンラインで受けられる。
日本語で楽ちん。
デメリット:
訓練費用が600万円を軽く超えそう。 - フィリピンの日本の会社が経営母体っぽい訓練校
メリット:
日本人教官も居て、国内の親会社の担当者とも話せた。
訓練費用が安そう。時差1時間。
デメリット:
訓練を行う空港まで、マニラのニノイ・アキノ国際空港から陸路で4時間以上を要する。
訓練を受けるためのSSP(Special Study Permit)というものを取得するためにパスポートを預けるため、フィリピンに2〜3週間滞在しなければいけない。
得られるのはフィリピンのライセンス。
座学が英語とはいえ、フィリピンのものなので情報が少ない。追加費用を支払い座学を1:1のオンラインで受けて希望の時間に行って貰えるように交渉はした。 - ホノルルで体験操縦をさせてもらったところ
メリット:
日本人経営者で、その方もアメリカでPPLを取った人。話して良い人だなと思った。
FAAのライセンスが得られる。FAAなので情報が豊富。
デメリット:
時差-19時間。
日本からのフライトが7時間以上。
訓練校のあるダニエル・K・イノウエ国際空港が混雑していて、特に訓練初期は苦労しそう。 - グアムの訓練校
メリット:
日本人経営者っぽい。日本人教官も居る。
FAAのライセンスが得られる。FAAなので情報が豊富。
時差1時間。
日本からのフライトが3.5時間。航空券も安め。
デメリット:
グアムが準州で、ちょっと扱いが微妙。チェックライド(実地試験)のときに試験官をハワイから呼ばなければならなかったり、飛行機を借りるときのAOPA Aircraft Renters Insuranceが有効で無いという情報を目にした。
海外で訓練を受けるのであれば、ワーケーション的に仕事をしながら飛行訓練を受けたいのでオンラインで座学を受けられるところを探した。1は座学の学習教材を独自のオンライン教材で提供していて、たまたまそれの存在を通じて知った訓練校である。2のフィリピンの訓練校については交渉をしたが、ここは教官がオンライン会議ソフトを使って講義を行う形式なのであまり融通は利かなさそうだった。3と4の訓練校とは共にPart 61の訓練を提供している様だ。
Part 61とPart 141
Part 61というのはFAR(Federal Aviation Regulations、連邦航空規則)のPart 61のことで、ここではパイロットの受験資格などについて既定がなされている。よくこれと比較されるのがPart 141の訓練校で、こちらはPart 141で既定されているフライトスクールの要件を満たし、決まったシラバスやスケジュールに基づいた訓練を提供している。Part 141の訓練校は一般的にフルタイムで受講をしなければならないが、要求されている飛行時間も少なく、短期間でコスト効率良く訓練が進むそうだ。これに対してPart 61の訓練校はフレキシブルに自分の都合で訓練を進めることができる。先に書いた様にワーケーション的に仕事をしながら飛行訓練を受けたい僕としてはPart 61の訓練校のほうが合っていると思う。
アメリカでFAAのライセンスを取るとアメリカで飛行機を借りて飛ばすこともできるようになる。またPart 61の方向で進めば座学については本やオンライン教材を使って自習、Written testという試験会場にあるコンピューターを使ったテストを教官からのEndorsement(承認)を得て受験するという仕組みであるために自分のスケジュールに合わせて物事を進められるのが良い。特にFAAのPPL(自家用操縦士ライセンス)についてはFAAが過去問を公開しており、様々な模試も存在し、日本人が訳をつけた問題集を公開していたりもするので自習が非常に容易である。
オンライン座学コース
僕は訓練校を探している間に次のオンライン座学コースを見つけた。
- Angle Of Attack – Online ground school $279
アラスカにある訓練校が提供している。出演しているChris Palmarさんは航空に進む前は映像制作の教育を受けていたということもあり、なかなか魅せる動画教材が提供されている。ただし動画教材のみで、模試などは無い。
西洋人らしいフランクな雰囲気でとても良いのだが、ノンネイティブとしては字幕があったらもっと良かったと思う。 - Sporty’s – Learn To Fly Course – Private Pilot Ground School $299
パイロット向けのオンラインショップっぽいSporty’sが提供しているオンライン座学コース。動画教材の下に要点をまとめたノートが付いていたり、コマによっては知識確認テストがあったり、模試があったり、進捗をCFI(教官)に共有する機能があったりと高機能。ただし至って普通の教材ビデオ。ノンネイティブにはありがたい英語字幕も出せる。コース修了後にendorsementをいただけるので、たぶんそれをもってwritten testを受けることが可能。 - KING Schools – Private Pilot Online Ground School & Test Prep $299
大変にアメリカンなオンライン座学コース。memory aidがちょっと良いなと思った。サンプルを見る限り字幕は無い。こちらもコース修了後にエンドースメントを貰えそう。 - ASA – Private Pilot Online Ground School $179.95
自習の参考書として頻出のASAによるオンライン座学コース。他社よりも安めだが、24ヶ月アクセスという条件がついている。本は買おうかと考えたが、コースは中身を見ることができないので試していない。 - Pilot Institute – Private Pilot Made Easy Online Ground School. $225
ページ下方に”Free Lesson Preview”があるので見てみたところ、字幕の表示が可能。アメリカの大学の先生の授業(実際に講師はそうらしい)らしい雰囲気のビデオだった。個人的には良さそうだと思った。 - Rod Machado’s 40-hour Private Pilot eLearning Ground School $279
サンプルを見て、説明に例えが多く遠回りに感じたので購入しなかったオンライン座学コース。人によってはこちらのほうが分かりやすいと思うかもしれない。サンプルはVimeoにアップロードされていたので自動生成の字幕が出せたが、購入後のコンテンツにも字幕があるかどうか不明。
現状
こうして、1〜4までの訓練校にそれぞれ問い合わせをして、検討を重ねて4のグアムの訓練校で訓練を受けようということに決めた。なお、オーストラリアやカナダの訓練校も検討はしたが、アメリカのPart 61の訓練校のようにフレキシブルでなさそうなこと、それに伴いビザが面倒そうなこと、どうせ取るなら日本以外ならアメリカのライセンスが有効活用できそうなことを理由に除外した。
座学コースはSporty’sのもので順調に進行中。
アメリカで訓練を受けるには、911によって生まれたTSA(Transportation Security Administration、運輸保安庁)のFlight Training Security Programの許可を得る必要がある。申請はFTSPのサイトで行い、申請が完了したら指紋採取を行ってもらう様だ。指紋採取はNATA FTSP Collection Informationで申し込む。日本には3名指紋採取をしてくださる方が居るようだが、僕はまだFTSPの申請を行ったばかりなので指紋採取に進んだところで改めて報告をしたい。
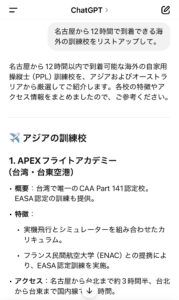
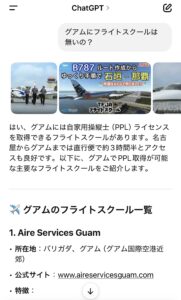


0 Comments.